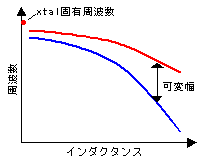
VXOは可変周波数水晶発振器(Variable Xtal Oscillator)の略で、名前の通り水晶発振器でありながら周波数を可変できる発振器である。水晶の安定性と可変発振器の利便性を目的としていて、無線には昔からよく使われる。通常はコルピッツ発振器の水晶にコイルとバリコンをシリーズに接続することで実現することが多いようだ。
コイルは非常に重要な要素で、可変幅や安定度に影響を与える。インダクタンスと周波数、可変幅のイメージは下図のようになる。一般に、安定動作を行うVXOの可変幅は水晶固有発振周波数の0.5%程度であると言われている。インダクタンスを増やすと、明らかにこれを越える可変幅が得られるようになる。しかし、この領域では水晶発振をかけ離れて動作しており、もはやLC発振になっている。DACでは、カテゴリ2でもプラマイ1000ppm(0.1%)のロックレンジが確保できればよく、0.5%の可変幅はおつりがくる。
周波数偏差とインダクタンス
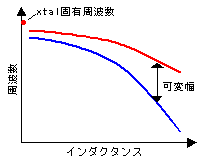 |
PLLのVCOとしてVXOを用いる場合、電圧で周波数を変化させるためにバリコンをバリキャップに置き換える。このため、VCXO(Voltage
Controlled variable Xtal Oscillator=電圧制御可変水晶発振器)という。バリキャップにかける電圧範囲が広いほど、広い可変領域が確保できるのはいうまでもない。
調整幅が広く、制御電圧に対して周波数が直線的に変化するためにはバリキャップに負バイアスを与え、オフセット調整も負バイアスで行う方式が良いと思われる。また、可変幅の調整はコイルで、周波数の微調整は負バイアスと役割を分けることで設計及び調整も楽になる。
しかし、負電源をもうけることが面倒なため、バイアスを与えずにバリキャップのアノードをそのままGNDに落とした。上図を見ても明らかなように、この回路構成ではインダクタンスに周波数微調整と可変幅調整の役割が生じるため、xtalの固有周波数をシビアに選定する必要が出てくる。つまり、プラマイ1000ppmの可変幅と中心周波数384fsを同時に満足するように水晶発振子とコイルの定数を選ばなければならない。
また、バリキャップ規格表の低電圧側が2Vになっていることから予想されるように、バリキャップに低い電圧を加えると特性(特に直線性)が悪くなることも考えられる。しかし、PLLではVCOの直線性はあまり問題にはならない。
定数は実験の繰り返しによって得ることが必要であった。たとえばCDのようにfs=44.1KHzの場合は384fs=16.9344MHzであり、これを可変幅の中心周波数とする。バリキャップに加える電圧を0-5vで変化させ、変移が2000ppm程度になるようにコイルと水晶を選択する。変移はだいたいでよく、1500程度から3000ppmにあれば良い。また、コアの位置を大きく変化させても5000ppmを越える変移領域入らならないようにしたほうが良い。
この作業を32KHzと48KHzのVCXOでも行い、最適なコイルと水晶を選択する。最初は水晶を目的周波数(384fs)の0.5%高めで作成し、最終的なものは実験で適切な周波数を再計算して発注した。様々な巻き数のコイルと組み合わせ、数十回の実験で出てきた定数は以下の通りであった。
| fs | 384fs | コイル巻数 | 水晶周波数 |
| 32KHz | 12.288MHz | 44回 | 12.334MHz |
| 44.1KHz | 16.9344MHz | 27回 | 16.975MHz |
| 48KHz | 18.432MHz | 25回 | 18.482MHz |
実験回路
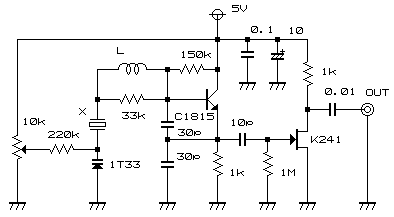 |
特注した水晶振動子
 |
実験中の基板(と転がるコイル)
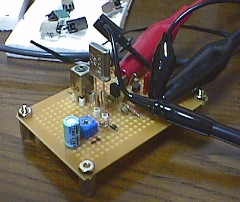 |
| 型番 | 用途 | VRM
(V) |
VR
(V) |
端子間容量
min(pF) |
端子間容量
max(pF) |
容量比 |
| 1T33 | Tuning | 35 | 30 | 27.19(2V)
2.71(25V) |
32.03(2V)
3.04(25V) |
10(2V/25V) |
ちなみに、コアの調整には専用のドライバーを使用すること。また、コアは非常に割れやすため回す時は気を付ける。適切でないドライバを使うと、簡単に頭が割れてしまう。