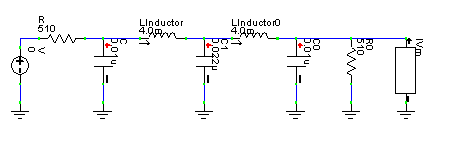
ΣΔ型DACではオーディオ帯域内の量子化ノイズをΣΔ変調により帯域外に押し出すため、オーディオ帯域外に大きなノイズが発生している。このため、ラダー型などのDACよりも重いポストフィルタが必要になる。
LPFとしてもっとも使われているのは電圧帰還型(バタワース型)で、それよりも急峻な特性が要求される場合はGIC型なども使われているようだ。これらはオペアンプなどによるアクティブフィルタである。また、パッシブ型としては連立チェビシェフ型も使われる。ただし、最近の機器にはこれはあまりないようだ。オーバサンプリングが無い時代に20KHz以上を急激に減衰させるために盛んに使われていたようだが、通過帯域の特性にリプルがあるため嫌われたのだろう。
SM5864のデータシートにはノイズシェーパの発生するノイズスペクトルに関するグラフがついている。それによると、16ビットの量子化ノイズを0dBとして、2fs時に40dBのノイズ成分が発生することがわかる。1fs時に5dB程度であるから、LPFに要求される遮断特性は-35dB/oct程度であることがわかる。
通過帯域の偏差は最大でも0.2dB程度に押さえたい。これはあるオーディオ評論家のヘッドホンを使うと0.2dBの音量差がわかる、という言葉による。ホントか嘘かは知らないが。0〜20KHzまでは0.2dB以内の偏差とする。カットオフ周波数は一般的に-3dB点であるが、これは25K〜30KHz程度になると思われる。
上記のような条件をふまえ、なるべく部品を減らすことを目標としてメインLPFは2段π型とした。π型のフィルタ特性は-18dB/OCTであるから、2段かませば単純計算上-36dB/OCTになるはずである。DACのフィルタをπ型にした例は聞いたことがないが、部品点数が少なくてすむこと、設計が簡単であることが大きな魅力である。π型フィルタはオーディオでは電源のリプルフィルタ、高周波では送信機のフィルタとしてよく使われる。
π型フィルタの設計は簡単で、ラインインピーダンスとカットオフ周波数を決めた後、コンデンサとコイルのインピーダンスがカットオフ周波数でラインインピーダンスと等しくなるようにするだけである。つまり、
| Z=ωFL=1/ωFC
Z=ラインインピーダンス
|
が成立するように値を出すだけである。
また、π型フィルタの挿入損失は-6dBである。
ラインインピーダンスを600オーム、カットオフを30KHz程度として机上計算を行って定数を得た後、SPICEにかけて特性を見ながら定数を追いつめた。コイルは自分で巻くから任意の値(ただし巻ける範囲内)で良いが、コンデンサ(それもフィルムコンでオーディオ用)の容量は選択肢が少ないため、コンデンサの容量をまず固定し、ラインインピーダンスを含めたあちこちの定数をいじって最終値を決めた。
最終的にはラインインピーダンスが約500オーム、コイルは4mH、コンデンサは0.01uF/0.022uFとした。本来はπ型2段重ねの真ん中にあるコンデンサは端のコンデンサx2であるから0.02uFであるが(両端のπのコンデンサを兼用するため)、0.02uFというコンデンサは入手できなかった(おそらく作っていない)ので、0.01uFx2ではなく0.022uFx1とした。これは部品を減らすためである。この定数変化もふまえ、シュミレーションしている。
SPICEにかけた回路と遮断特性を示す。
シミュレータ上の回路
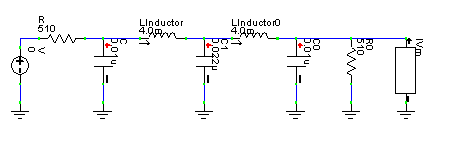 |
遮断特性(電圧源は2Vrmsに設定)
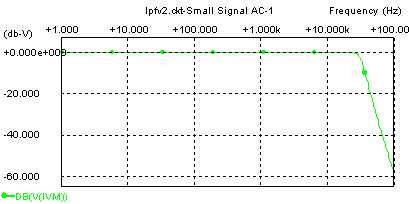 |
遮断特性の拡大(電圧源は2Vrmに設定)
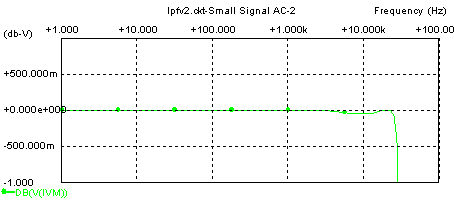 |
遮断特性とノイズシェーパのスペクトルを重ねてみると以下のようなグラフになる。
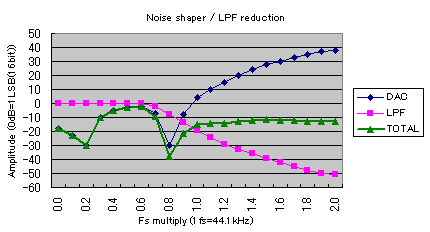 |
緑線がローパスフィルタ後の出力であるが、オーディオ帯域外でも16ビットの量子化ノイズを下回っており、設計上は十分に機能している。ノイズシェーパのノイズとLPFの遮断特性がマッチしているから1fs以上はほぼスペクトルが直線になっている。ただし、実際には2段π型LPFのほかにも差動アンプ周りにCR型のパッシブLPFがつくため、これよりも大きな減衰特性になるはずである。